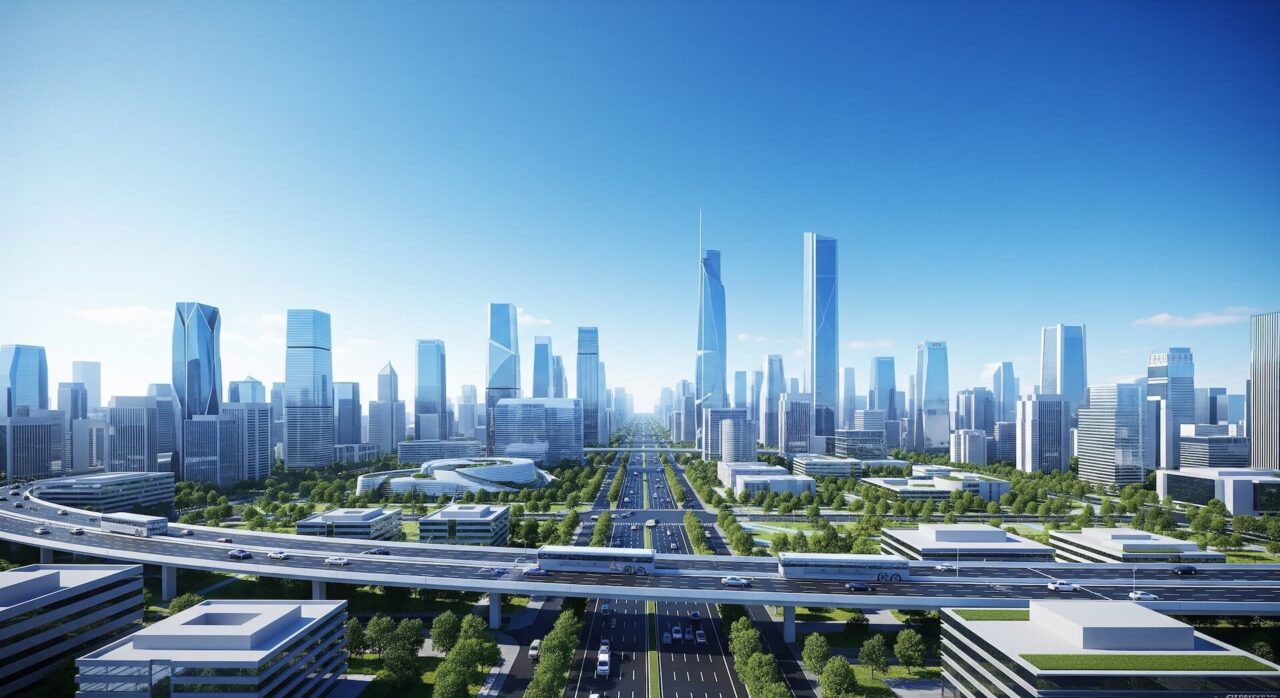人生の様々な場面で、親族からまとまった資金援助を受けることがあるかもしれません。しかし、そのお金のやり取り、「贈与税」について深く考えたことはありますか?安易な資金移動は、後から税務署に「贈与」と見なされ、思わぬ高額な税金が課されるリスクがあります。本当に重要なのは、契約書の有無よりも「現実的な返済計画」と、それを「実行した証拠」です。この記事では、親族間の資金移動で失敗しないための鉄則を、実務上のリアル事例を踏まえながら税理士の視点で徹底解説します。

なぜ?親族間の資金援助で「贈与税」が問題になるのか
親族間でまとまったお金が動いた場合、税務上のポイントは非常にシンプルです。それは「あげたもの(贈与)」なのか、「貸したもの(貸借)」なのか、という点です。
もし「贈与」であれば、年間110万円の基礎控除額を超えた部分には贈与税が課税されます。一方で「貸借」であれば、それは単なる借金ですので、贈与税はかかりません。
特に親族間では、「あるとき払いでいいよ」といった曖昧な約束でお金をやり取りしがちです。しかし、返済の約束が不明確な、いわゆる「あるとき払いや出世払い」は、税務上の考え方の根底は「贈与」であることを、大前提として知っておく必要があります。
参照:国税庁 タックスアンサー No.4420 親から金銭を借りた場合
「貸し借り」の証明に。金銭消費貸借契約書はあった方が良い?

「贈与ではない、借りたお金だ」と主張するため、金銭消費貸借契約書を作成するケースがあります。しかし、ここで非常に重要な点をお伝えします。契約書は、法的に絶対に必須という訳ではなく、また、それ自体が貸借の強力な証拠になるわけでもありません。
あくまで、契約書は形式的な補助的資料の一つという位置づけです。税務調査で最終的に、そして最も重視されるのは、次に解説する「返済の実態」に他なりません。 そのため、契約書は「あればなお良し」程度に考え、その作成に満足してしまうのではなく、最も重要な返済計画とその実行にこそ、注力するようにしてください。
【最重要】契約書より大事!贈与認定されないための2大鉄則
ここからが本題です。税務署が贈与かどうかを判断する際、契約書の有無にかかわらず、決定的に重視するのが「貸借の実態」です。その実態を示すために、以下の2つの鉄則は必ず守ってください。

鉄則①:誰が見ても「現実的な返済計画」を立てる
まず大前提として、立てた返済計画が借主の収入や資産状況に対して現実的であることが不可欠です。例えば、高額な資金を借りたにもかかわらず、返済が月々数千円といった極端に少額で、完済に非現実的な長期間を要するような計画は、「本当に返すつもりがあるのか?」と、その意思を疑われても仕方がありません。
ご自身の収入から無理なく返済できる範囲で、社会通念上、妥当な期間で完済できる計画を立てましょう。
鉄則②:計画通りに「返済した証拠」を通帳に残す
そして、これが最も重要です。立てた計画通りに、きちんと返済を実行し、その証拠を残し続けることです。
最も確実な方法は、銀行振込を利用することです。これにより、「いつ、誰が、誰に、いくら支払ったか」という事実が、あなたの通帳に明確に印字されます。この通帳記録こそ、客観的な証拠となります。現金での手渡しは記録が残らず立証が困難になるため、避けた方が良いでしょう。
「現実的な計画」があり、それを「通帳記録で証明」できる。この2つが揃えば税務署に対して「贈与」ではないと主張することも不可能ではないでしょう。
税理士が見たリアル事例:兄弟間での相続税立替

この「現実的な返済計画と実行の証拠が最重要」という考え方は、税金の立替払い等の資金移動にも当てはまります。ここで、私の実務上でのリアル事例をご紹介します。(※プライバシー保護のため、登場人物や設定は一部変更しています)
ある相続で、ご長男のA様はご実家の不動産(家賃収入のある収益物件)を遺言により相続されましたが、現金の相続が少なく、納税資金が不足しているという事例でした。一方で、同じく相続人であるご次男のB様は、遺言により現金を多く相続されており、兄弟間でどうにかできないかと頭を悩ませておられました。(長男に不動産を、次男に現金をという遺言は、実務上よく見られます)
そこで実行していただいたのが、まさにこの「貸し借り(立替)」という方法です。まず、A様の家賃収入から無理なく長期間で返済できる現実的な返済計画を策定。その上で、A様とB様の間で正式に金銭消費貸借契約書を交わしていただきました。
そして現在も、A様は計画通りにB様の口座へ毎月の返済を銀行振込で続けておられます。これにより、B様からA様への資金移動は「贈与」ではなく、明確に「貸付」として定義しました。結果、A様は贈与税の心配をすることなく、無事に相続税の納税を済ませることができたのです。
このように、実際の現場においても、契約書の存在以上に「現実的な計画」と「継続した返済の事実」こそが、税務上の判断を左右する決定的な鍵となるのです。
まとめ
親族からまとまった資金援助を受ける際、それを「贈与」と見なされないために最も重要なポイントは2つあります。それは「①現実的な返済計画」と「②計画通りに返済した客観的な証拠」です。
金銭消費貸借契約書は、貸借の意思を示す上で有効なため作成を推奨しますが、それ自体が目的ではありません。契約書があっても、計画が非現実的であったり、返済の実績が伴わなかったりすれば、贈与と判断されるリスクは残ります。
安心して資金援助を受けるために、以下のチェックリストを必ず確認してください。
- 現実的な返済計画を立てていますか?
- (推奨)貸借の事実を明確にするため、金銭消費貸借契約書を作成しましたか?
- 返済は銀行振込で行い、通帳に記録を残していますか?
これらの点を確実に実行することが、将来の税務リスクを避ける最善の策となります。
親族間のお金の貸し借りについて、ご自身のケースではどうすれば良いかご不安な方は、税理士などの専門家にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスがもらえます。
この記事に関するご質問や、あなたの体験談もぜひ下のコメント欄でお聞かせください。
税理士 今北 有俊